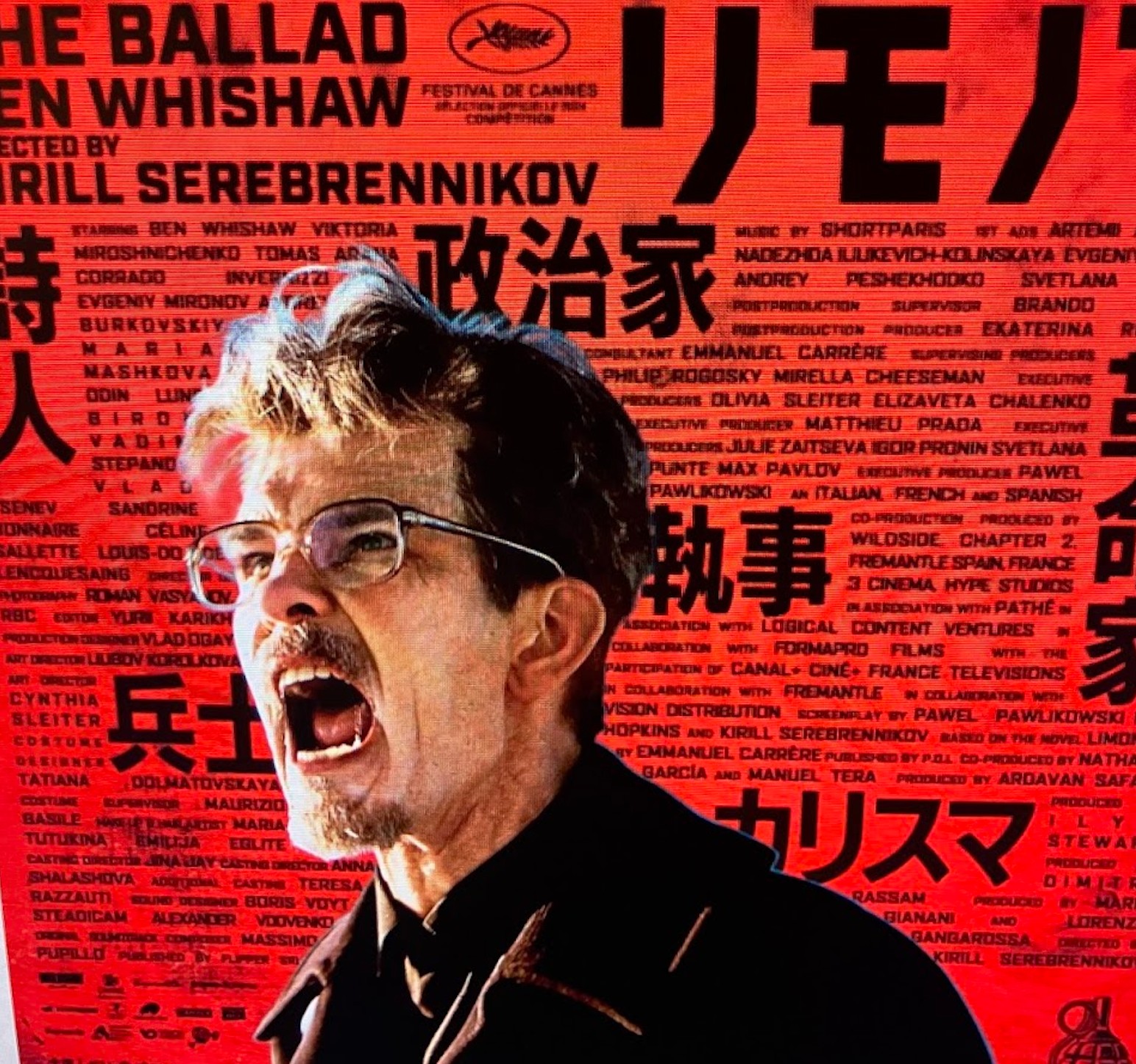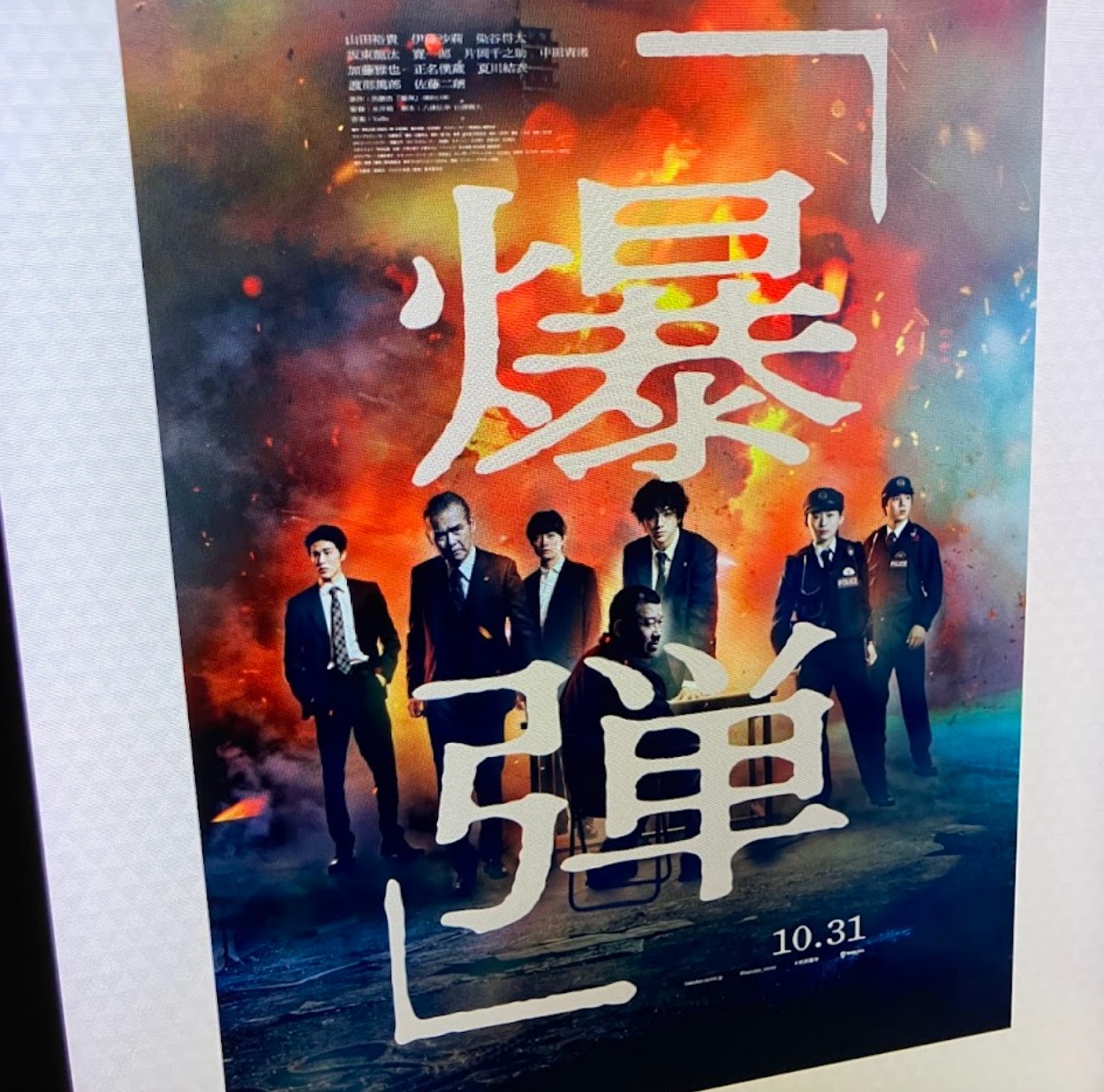相席食堂でカナメストーンがハネて、千鳥に評価された時間、長年ファンやってた俺たちへのご褒美のように感じた。「信用してるから、両方前向けてる」とか、慧眼だった。確かになー。同業じゃないと気づきづらいポイント。
https://www.instagram.com/p/DUheJHfiSrI/
トキと錦織さんだけがヘブンさんの真の気持ちを理解できていないのも面白かったし、トキがそれに気づく演出でも直接的な言葉は使われなかったし、最後にそれを伝えるよう促すのが事もあろうにラストサムライだったのも熱かった。あの時のヘブンさんの苦悩の顔は実に男前で、役者が役に追いついたタイミングだったかもしれぬ。『ばけばけ』、相変わらず丁寧で素晴らしいです。
法事が終わったら、今度はインフルにやられて、床に伏せたり、無理矢理仕事したりしてました。なんなんだ今年。何もできぬ間に、いつの間にか2月になっていた。かつてそういう年(1月からインフル)があって、さぞかし酷い年になるだろう、と恐怖していたら、意外と良い年だった記憶。
ようやくインフルが引けてきたので、昨晩は久しぶりにベースをレコーディングした。
「亡くなる時に人の真価は問われるのだな」とか、答え合わせのように思っていたけど、いやそれだけではなくて、どこでどのように生きてきたかとか、人に依存して生きてきたのか、他人が自分に依存していたのか、とか。そんな様々の条件が蠢いて、死の瞬間が形作られていくのだ、と感慨深く思いながら、妻のお父さんの葬儀を見守ってきました。その直後に、今度は自分のおばさんが亡くなり、訃報が連続した(結局、参列出来なかったのが残念だった)。重なるもんなんですね。
『令和ロマンの娯楽がたり』を観たが、いまいちピンと来ず。お笑い業界の演者たちが、自分たちのことを自分たちで語り、外部からの声はかなり権威主義的にシャットアウトするやり口に対してぼんやりと感じていた不信感が、一年を通して決定的になってしまったのがデカそう。
加えて「みんなで正解を議論しよう」という建付けで求められている「俯瞰」と「客観視」の白々しさが、画面中の擬似的な熱狂と乖離して、浮き彫りになってしまっているように見える。生成AIが幅を利かせ始めたこの時代に、「正解」になんの意味があるのか。時流とか、ビジネスよりも、主観の大間違いに価値があるという、いつもの話。
李龍徳『あなたが私を竹槍で突き殺す前に』

「排外主義者たちの夢は叶った」という書き出しがあまりに鮮烈なのだが、その切れ味が以降のページでも一向に収まらない。この「憤り」の物語は、複雑な双方向の刃で周囲に切り掛かり、その様が如何にもSNS以降の「現代」という空気を感じさせる。
「極右の女性政治家」が総理大臣となり、排外主義が幅を効かせた結果、在日韓国人の人権が脅かされていく。2020年の作品とは思えないほど、現代日本を言い当ててしまっていることに怖気を感じるが、現実同様、外も内もザリザリにささくれ立っていく中、韓国への集団帰国を企てる「青年団」の元リーダー朴梨花の言葉がよかった。彼女は、政治活動を創作活動の一つの発露として捉えている。
でも私は気づいたの。直接の読者を持たないような、私のなかだけで閉じているように思われる自称『創作活動』がそれでも、この世界の扉をノックしてた、この世界にじかに触れてた、世界に参加してた、って。そうじゃなかったらどうして、(中略)後世に作品を残せなかった名もなき作り手たちの声が、私たちの礎となったと言えるか。この世界を動かす。私たちの住むこの大きな球体をなんとか動かす。その指の引っかかりとなる。
フリーダ・マクファデン『ハウスメイド』

「登場人物一覧」に記載されている人数を無視できるミステリー好きはいない(断言)。ここに記載されている中に真犯人は含まれる(含まれていない場合、激しい非難の対象となる)ため、数が多ければ複雑で読み甲斐があり、少ないと単純で退屈、と予想可能だし、その予想は大抵当たる。だからフリーダ・マクファデン『ハウスメイド』の登場人物一覧に記載された人物が「5人」というのは大変危険な信号。しかし、ここまで少ないのは未だかつて見たことがない。であれば、むしろ挑発的、とも感じられた。
結論、大いに挑発的だった。主人公の家政婦ミリー、勤め先の富豪アンディ夫妻に、娘と庭師。完読すれば、ここに追加できる人物がもう何人かいることに気づく(近隣の住人や、アンディの両親など)が、むしろこの5人であることが重要。ミスリーディングもテーマのブレも避け、不気味な家に住み込みで勤めることになったミリーの不安にフォーカス出来る、�ベストな登場人物一覧である。
中身はすごい。近年の端正な構造を持ったミステリーの数々に比べると荒削りではあるが、ショートショートの連続のようなスピードで不穏な小話が挿入されて、すべてをすっ飛ばしてオチを聞かせて欲しい気持ちでたまらなくなる。その衝動が燃料となり、ページを繰る指が止まらない。そんなタイプのスリラー。
映画向きだなー、もっと言うと端から映画化を目論んで執筆されたような作品だなと思っていたら、2025年の12月、既に公開されているとのことで。

ミリー役シドニー・スウィーニーかーーーー。ケイリー・スピーニーで想像していたんで調子狂ったなー、とか思いました。
歌詞完成ー!疲れたー!やったー!

謹賀新年。と言っても、何の節目にもなっていないので、そこまで前のめりになっているわけでもなく、引き続き淡々とやることやるぞ、と。昨年出そうと思った音源はちょい遅れて、ようやく歌詞が7割終わったぐらいで詰め作業中。全部が終わるのは3月ぐらいになりそうなので、そこまでは一続き感が拭えないのだろうなと思う。
時宜にそぐわぬと承知の上で年始からこんなこと言うのだが、一年一年死が近づいている。やれることは少な��くなってくるから、やるべきことを優先的に取り組むしかない。
ここ二週間の薄皮を重ねていくような丁寧な描写の果てに迎えた今日の『ばけばけ』。直接的な一言はついぞ吐かれることないまま、ある想いの成就は完璧に納得させられる。それを支える、演技、カメラ、音。そしてオープニングクレジットにはいつもの写真はなく、逆光に佇む二人の姿が重なっていく。エンドロールかと思ってしまいました。
M-1グランプリ2025。2008年の敗者復活、その頃は中継もなく、今も続けている「M-1の日は大掃除をする」という習慣に従って、大井競馬場の様子をタイムラインで伺いながら歓喜したオードリー以来の、「推しのコンビが敗者復活から決勝進出」という至福を味わった。あんまり冷静ではなかったかも。
翻って、本戦。今年は本当に、過程が良かったですね。そういう意味では、2019年(ミルクボーイ)、2021年(錦鯉)に匹敵するものがあった。下馬評は、真空ジェシカ、エバース、ヤーレンズ。三組とも爆発したが、その中でも最も火力の高かったエバースが抜けて、後は初進出組というバランス。M-1は、熟練の技術を楽しむ場であるのと同時に、新味も非常に重要であることは御存知の通り。そういう意味では、「売れてない中堅〜ベテラン」の有利が味方する。正直、ドンデコルテの成長と爆発には仰天してしまったが、それ以上に爆発したたくろうの優勝は納得しかない。これに関しては駒場さんの審査コメントが非常に的確だったことに感心している。挙動不審の人間を笑うネタに見えるのだが、人の話も聞かず狂っているのは完全にきむらバンド。狂人に踊らされた赤木は、ボケとツッコミの両方をやらされる羽目になってしまう。妻はもう数年来のたくろうファンなので、結果に泣いてた。
カナメストーンは、二人の良さが伝わる形で決勝に出られて本当に良かった。もちろん、最高の結果とは言えないかもしれないけど、十分な結果。売れた。また好きなコンビが売れてしまった。今は寂しさよりも嬉しさが勝っている。相席食堂が楽しみ。いつもカナメちゃん村で泣き出す零士をやさしく受け止めてるヤーチーが、場面場面で今にも落涙するかのように感極まっている珍しい光景を観て、しみじみしてしまったな。
今朝の『ばけばけ』、しじみさんとヘブン先生の部屋が画面中央で分けられ、暗い部屋から明るい部屋に足を踏み出す瞬間、使われる人間の領域から対等な関係になることを示唆している。すごくわかりやすいが、光を効果的に使った演出に感じ入った。いよいよ怪談を話す、という段になって、やおら立ち上がったトキは、簾を下ろして、屋内は一律に暗くなり、蝋燭の細い灯りの前に、どこか艶めいた顔を見せるのでした。