イギリスのアヴァンギャルドロックバンド「Black Midi」のギタリスト兼ボーカリスト。2024年に初のソロアルバム『The New Sound』をリリース。ポストパンク、ジャズ、ファンク、カリプソなど、多様なジャンルを縦横無尽に操る音楽性で注目を集めている。高速マシーン歌謡とも評される独自の音楽スタイルは、既存の音楽ジャンルの枠組みを超越している。
※ AIによる解説文(β)です。当サイトの内容を参照して、独自の解説文を構築していますが、内容に誤りのある場合があります。ご留意ください
My Best Contents 2024
今年も残すところあと三分。今年はアウトプット控えめに、とにかく言い訳できないぐらいインプットしてやろうと心に決め、結果450本も映画を観ることができた。それで分かったんですが、この定額配信時代、映画を沢山観るだけなら誰でも出来る。そこから何を受け取り、何をアウトプットするかが一番重要で、�それ以外は本数に何の意味もないです。それが分かってよかった。来年はゴリゴリアウトプットしていきますので、何卒よろしくお願いいたします。
俺デミー賞2024
10. システム・クラッシャー
自らの怒りを制御できない子どもを前にして、大人は如何に振る舞うべきか、我々の倫理観も問われる物語。全ての甘い退路が一つずつ潰れていく絶望感。この作品は、安易に答えを出すことを許してくれない。
https://www.rippingyard.com/post/Ed6U2ECq33oatdLJnUIO
9. フォールガイ
この手の映画が好きだった母親のことも思い出してより感情が昂ってしまったのはあれど、あの頃、こういうイカした映画って沢山あったよなー的錯覚(今も良い映画は沢山あるので)に陥ってしまうぐらいの、突き抜けたアクション快作。
https://www.rippingyard.com/post/9HIiBgQgOMKy9WtVJLqr
8. インフィニティ・プール
ディストピアSF的な設定の妙とか、脚本の良さもあれど、それを上回る暴力的なテンションといいますか、作り手側の過剰な昂りを感じてしまう。現代最強女優の一人、ミア・ゴスがそれをさせている。
https://www.rippingyard.com/post/o8mcsYMKJfaSf3SUvdRG
7. 悪は存在しない
世界の混沌を見かけ上の静謐に押し込める。直前に観たゴダールとも見事にリンクした、淀みの連鎖。この毒に対する観客各自のリアクションが、ラストの解釈の多様に結びついていくのではないか�。
https://www.rippingyard.com/post/ff4zDJvQaG8X6y8axqci
6. 二つの季節しかない村
ヌリ・ビルゲ・ジェイランのことは、半分ギャグ作家だと思ってる。ここまで性格の悪い人間が主人公だと、ここまで場が荒れるのだ、と感心。3時間は敬遠しがちだが、超性格悪い人の滑稽な所作が観れるとなるとこれでも短いのではないか?
https://www.rippingyard.com/post/QxaIPEtXwjw2iHAncx8W
5. 夜明けのすべて
素晴らしい演技、素晴らしい脚本、素晴らしい撮影に加えて、素晴らしい事後鼎談。なんか他に言うことある?客観的に見ると、今年の邦画ナンバーワンだと思う。
https://www.rippingyard.com/post/NRhfrQ8vDQVGkq8C8KRS
4. 墓泥棒と失われた女神
『チャレンジャーズ』に続けて、俺の中でジョシュ・オコナーの名が特別なものになった(『ゴッド・オウン・カントリー』も素晴らしかった)。今後もとんでもない映画を撮り続けるであろうアリーチェ・ロルヴァケルにとっては、通過点なんだろうなあ。
https://www.rippingyard.com/post/PeKiy4Ip6gXien7w3olR
3. 憐れみの3章
若輩者の俺はまだまだ深淵には迫れなかったが、その後、レビュー読んだり、町山さんの解説を聞いていたら、古代ギリシャ悲劇に通じていればもう少し理解は進みそう。こういう世界の広がりを感じさせてくれる作品が好きだ。個人的にはランティモスのベストかなーと思う。
https://www.rippingyard.com/post/yVYIowg4AOyU4OqyO2t9
2. 若武者
どうしても外せなかった一本。ここで展開される邪悪な屁理屈と、シンプルな日常描写は、鋭利な現代日本批評になっていると思うし、それをここまで直感的に面白く料理できるのはかなりの手腕だと改めて思う。
https://www.rippingyard.com/post/C4XFoBPQerLUpTBMg5oZ
1. グレース
圧倒的。視覚的な美しさと、肥溜めの中に咲く花のような瞬間が見事に交差して結びついている。こういう体験をするために、俺は映画を観ている。
https://www.rippingyard.com/post/DJbmrdFrBkk5mRsYkvk5
よく聞いた音楽
youra、Tyla、Caoilfhionn Rose、ナルコレプシン、デキシードの新譜、Geordie Greep、JW Francis、山二つ、fantasy of a broken heart、Bananagun、ALOYSE辺り。中でもベストアルバムは、Being Dead「Eels」。
印象的だった本
レイモンド・カーヴァーや今村夏子を再発見したり、相変わらずJホラーが充実してたりと色々ありましたが、特に印象深かったのは、ナージャ・トロコンニコワ『読書と暴動』とか、野矢茂樹『言語哲学がはじまる』、『優等生は探偵に向かない』辺り。
2024-12-31 15:10- 映画
- システム・クラッシャー
- フォールガイ
- インフィニティ・プール
- 悪は存在しない
- 二つの季節しかない村
- 夜明けのすべて
- 墓泥棒と失われた女神
- 憐れみの3章
- 若武者
- グレース
- チャレンジャーズ
- ジョシュ・オコナー
- ゴッド・オウン・カントリー
- アリーチェ・ロルヴァケル
- ランティモス
- Being Dead
- Eels
- youra
- Tyla
- Caoilfhionn Rose
- ナルコレプシン
- Geordie Greep
- JW Francis
- fantasy of a broken heart
- 山二つ
- Bananagun
- ALOYSE
- ナージャ・トロコンニコワ
- 読書と暴動
- 野矢茂樹
- 言語哲学がはじまる
- 優等生は探偵に向かない
- レイモンド・カーヴァー
- 今村夏子
- Jホラー
- Film
- Music
- Book
うんうんと唸りながら曲を作っているんだけど、今日ふと4曲(うち1曲はインタールード的なものなので、実質3曲)合わせて6分しかないことに気がついた。どういう計算?なんかエディットの密度が濃すぎるのだ。一生終わらないのではないか、という予感の中で創作作業を進めるのは気持ち良いので、このままやる。

BananagunのFree Energyを聴いて、EPに入れるか迷っていた曲をボツにした。この曲から、AloyseのIntentionに繋ぐプレイリストが完璧で、その道を探っている(それをナチュラルにやっているのがヒタ・リーなんだと思うんだけど)。この演奏を聴いていても、ドラムとパーカッションに比べて、上物の演奏レベルは決して高くなく、とにかくルーズなセンスだけでこの雰囲気を出しているのが理想的だな、と思う。Geordie Greepは最高だけど、一歩足を踏み外したらアスリート的になってしまう危険を孕んでいる。
昨日はNetflixで『喪う』、今日はU-Nextで『ピンク・クラウド』を観る。どちらも、狭い住居という限定された空間で撮られた(ほぼ)密室劇。故に、同じような気だるい閉塞感が立ち込めている。

寝る前に「おとうさんが、仕事の最中に流してる、あの曲、いい曲だよね。デデデッデデデッって曲」というので仔細聞いたら、Geordie Greepのことだった。その流れで、就寝直前の小学生にblack midiを聴かせる、など。
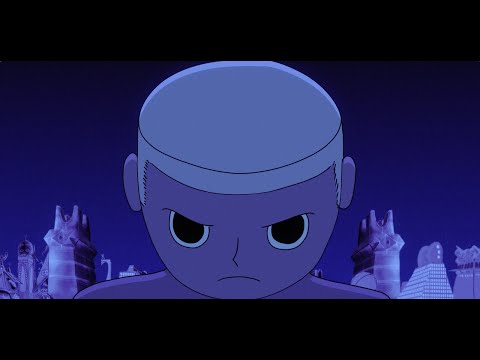

元Black Midi、Geordie Greepの初ソロ作『The New Sound』。Black Midiの作品より良いの、反則だと思う。前評判通り、ポストパンクの枷から逃れ、ジャズ、ファンク、カリプソ、サンバと凄まじい振れ幅のスタイルで、高速マシーン歌謡を構築。根っこには、オールディーズ好きがあると思うんだけど、そんな懐古趣味を反映したノスタルジー溢れるPVも良かった。来日ライブ、観たいな。

めちゃくちゃ美味いカレーを作って、むすこと食べた後、PFFアワード作品を観る。大学時代のサークルの先輩が高校の映画部顧問をやってるんだけど、教え子の作品が配信されていたから。その作品『ちあきの変拍子』観てると、もう高校生でこんな達者な映像を撮るんだ、と感心してしまった。イマジナリーフレンドをテーマにした脚本も上手いし、撮り続けて欲しいな。
フィリピンのスラムを映したドキュメンタリー『I AM NOT INVISIBLE』も続けて観たが、これがまた凄くて、人の住むところとは思えないような、地図にも載らない場所に暮らす人々が一様に「幸せ」を疑わない姿勢にドキッとさせられる。�今の日本で、あそこまではっきりと「幸せ」と言い切れる人はどれだけいるのだろうか。
この映画はそこで終わりではなく、フィリピン人の祖母との会話シーンで締められる。スラムの人々を「なまけもの」と非難する祖母との対話は緊張感に溢れている。「弱い人」と「強い人」の会話は、どちらが間違ってるとも言い切れない、微妙なスタンスの上を綱渡りし続ける。